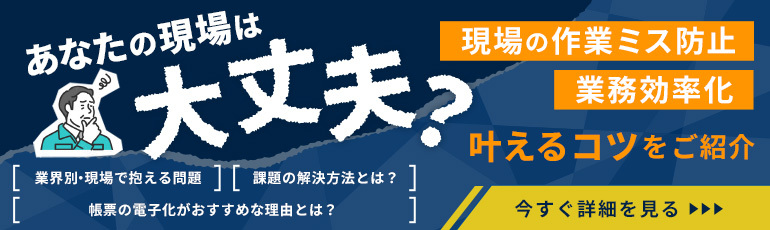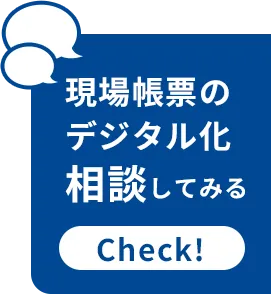目次
製造業や小売業にとって設備保全は、設備の安定稼働や製品の品質を維持し、生産性を向上させるうえで非常に大切です。ただし、生産設備が故障・不具合を起こしたあとに修理や交換を行っていると、予期せぬトラブルが生じた際に、生産ラインの停止などを引き起こし、大きな損失につながる恐れがあります。
このような状況の解決策として注目を集めているのが、「予防保全」と「予知保全」の2つの保全手法です。このコラムでは、小売業や製造業向けに、2つの保全手法の違いや特徴から、それぞれのメリット・デメリットまで、くわしく解説します。また、自社の設備や稼働状況に合わせて、最適な保全手法を選ぶためのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
予防保全と予知保全の違い
設備に故障・不具合が生じる前に予防的に点検や修理を行う、「予防保全」や「予知保全」に取り組む企業が増えています。
予防保全は、定期的に点検やメンテナンスを実施することで、故障を未然に防ぐ方法です。一方、予知保全は、センサーなどの機器やデータ分析を活用し、設備故障の予兆を捉えて対応する方法です。
それぞれの違いについてくわしくご説明します。
予防保全とは
予防保全は、あらかじめ策定された保全計画にもとづいて、点検や修理、部品交換を実施する、故障・不具合が生じる前に対処を行う手法です。具体的には、一定期間ごとに点検や部品交換を行う「時間基準保全」や、設備の状態を定期的に診断し、結果に応じて保全作業を行う「状態基準保全」などがあります。
予防保全は、設備の寿命延長や製品の安全性確保、生産性向上や突発的な故障の予防などを目的に行います。
予知保全とは
予知保全は、IoTセンサーやAI技術を活用して異常を察知する手法です。工場の機械・機器などの設備の状態を常時監視し、異常の兆候が見られた時点で対応を行います。
予知保全の目的は、設備の突発的な故障を防止し、生産性の向上や品質の安定化を図ることです。リアルタイムでデータを解析し、早期に異常検知して適切な対策を講じることで、設備トラブルを未然に防ぎます。
なお、設備の保全にはもう一つの方法があり、故障してから対応する「事後保全」です。次の見出しでは、事後保全の詳細をご説明します。
事後保全とは
予防保全と対照的なアプローチを取る事後保全は、設備や機器に生じた何らかのトラブルを発見したあとに、部品の交換などの修理を行う手法です。修理範囲が限定されるため、コストは低いものの、突発的な故障リスクが高まります。
主に、生産ラインの停止や安全リスクの影響が小さい設備で採用されています。
予防保全と予知保全のメリット・デメリット
予防保全と予知保全では、メリット・デメリットが異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 項目 | 予防保全 | 予知保全 |
| メリット | ・予期せぬ故障のリスクを低減 ・計画的な保全が可能 ・導入コストが比較的低い ・保全コストの予測がしやすい | ・設備のダウンタイムを回避 ・故障をより正確に予測 ・部品交換時期の適切化 ・データの蓄積と活用が可能 |
| デメリット | ・突発的な故障を完全に防げない ・不必要な点検・部品交換が発生する場合がある ・メンテナンス作業による生産停止の可能性がある | ・導入コストが高い (センサー、AI、ソフトウェアなど) ・データの解析スキルが必要 ・システムの運用や管理が複雑 ・予測の精度に依存する |
予防保全のメリットとデメリット
予防保全のメリット
定期的に点検や部品の交換を行うことで、設備の故障や劣化を早期に発見できるため、突発的な設備の故障を、未然に防ぐことが可能です。設備や機械の安定稼働を維持できるため、急な修理対応に追われることが少なくなります。
また、事前に策定された点検スケジュールにもとづいて定期メンテナンスを実施するため、作業の計画が立てやすいメリットも挙げられます。予想外の修理費や緊急対応費用を抑えられるため、予算管理がしやすくなるでしょう。
予防保全のデメリット
定期的に点検やメンテナンスを実施したからといって、故障や不具合が起こらないとは限りません。定期点検を行っていても、予想外の故障が発生する可能性があります。
また、まだ劣化していない部品を定期的に交換するため、余計なコストがかかることもデメリットです。
予知保全のメリットとデメリット
予知保全のメリット
予知保全では、異常が発生する前にメンテナンスを実施できるため、無駄な交換を減らせます。想定外のコストが発生しないため、メンテナンスコストの適切化が可能です。
また、各種センサやデータ解析を活用して、異常の兆しを検知することで、突発的な故障リスクを抑えられる利点もあります。過去の点検データや異常データを蓄積・分析することで、長期的な設備管理の精度を向上できるでしょう。
予知保全のデメリット
予知保全を行うためには、センサーの設置に加えて、IoTデバイスやAIシステムの構築、データ解析ツールの導入などが不可欠なため、初期投資が大きくなることがデメリットです。設備の異常を正確に予測するためには、高度な分析技術や人工知能の活用が必要になるだけではなく、専門知識を持つ人員の確保も求められます。
また、設備の状態を継続的にモニタリングするには、センサーやデータ管理システムのメンテナンス、ソフトウェアのアップデートやネットワーク環境の管理なども必要になるため、運用の手間が増えることもデメリットです。
自社に適した保全手法の選び方
保全手法の違いについては理解できたけれど、どちらを行えばいいのか悩む、設備管理者や経営者も多いでしょう。
短期的な導入のしやすさでは、予防保全が優れています。反対に、長期的に設備管理の精度を向上させ、コスト低下を目指すなら、予知保全がより高い効果を期待できます。自社の業務内容や設備の種類に応じて、両者を適切に組み合わせることが重要です。
予防保全が適しているケース
設備の故障が発生すると、大きな損失が発生するケースには、予防保全が向いています。
例えば、製造現場でラインが停止が発生すると、稼働時間が大幅に減少するでしょう。納期遅延が発生すると、取引先や顧客からの信頼失墜につながるようなケースでは、定期的な点検やメンテナンスでリスクを低減できます。
また、故障履歴が少なく、定期交換や点検によって、トラブルを未然に防げる設備にも向いています。法規制や安全基準により、一定期間ごとの点検が義務付けられているケースにも、予防保全は有効です。
予知保全が適しているケース
予知保全は、センサーやIoT技術を活用し、設備の劣化状態をリアルタイムで監視・検出できる環境が整っている場合に適しています。設備の稼働率が高く、稼働停止による影響が大きい場合には、適切なタイミングで保全を行わなければなりません。
他にも、故障パターンが明確であり、データ分析にもとづく予測が可能な設備に対しても、予知保全が適しています。
予防保全や予知保全で帳票システムを導入するメリット
予防保全と予知保全を効果的に実施するためには、帳票システムの導入が欠かせません。帳票システムを活用することで、データ管理の効率化や保全の精度向上、工数削減や作業負担の軽減など、さまざまなメリットが得られます。
データ管理の効率化で保全の精度が向上する
デジタル化された帳票システムを導入することで、点検結果や異常データを一元管理でき、必要な情報を迅速に検索・参照することが可能です。データ管理を効率的に行えば、設備保全を担当する従業員や作業員が、より多くの時間を設備の点検やメンテナンスに費やすことができるため、保全の精度が向上し、製造ラインの安定稼働を維持できます。
点検・異常データの蓄積と分析がしやすい
帳票システムで点検結果や異常データを一元管理し、収集・蓄積されたデータを活用することで、異常の予測が可能です。データ活用により、過去のデータを分析して劣化の兆候を捉えたり、適切なメンテナンス時期を判断したりすることが容易になります。
リアルタイム共有で連携を強化できる
クラウド型の帳票システムを導入すれば、点検結果や異常情報をリアルタイムで共有できます。保全担当者や管理者が生産現場にいない場合でも、即座に状況を把握できるため、迅速な対応が可能です。
設備停止のリスクを最小限に抑え、生産効率の向上に貢献します。
ペーパーレス化により作業負担の軽減につながる
従来の紙ベースの帳票管理では、記入や整理、保管などに時間と手間がかかる傾向がありました。デジタル帳票を導入することで、入力作業の簡略化や記録の自動保存、検索性の向上などにより、作業負担を大幅に軽減できます。
帳票の標準化で属人化を防げる
帳票システムを導入し、フォーマットを統一することで、点検や異常報告の基準が明確になり、個人の判断によるバラつきを防ぐことが可能です。新しい担当者への引き継ぎもスムーズにできるため、保全業務の品質を一定に保ちやすくなります。
予防保全・予知保全の効率化と精度向上に貢献する「i-Reporter」とは?
予防保全と予知保全はどちらも、設備の安定稼働と生産効率向上に不可欠な保全手法です。自社の設備状況や予算、人材や人件費などを考慮し、最適な保全活動の方法を選びましょう。
設備保全の効率化と精度向上を図るには、デジタル帳票システムの導入をおすすめします。現場帳票システム「i-Reporter」は、現場の点検業務の効率化とペーパーレス化を実現するツールとして、多くの企業に導入されています。使い慣れた帳票をデジタル化し、現場でのデータ入力が簡単に行え、リアルタイムなデータの共有が可能です。
ぜひ「i-Reporter」を導入し、設備保全業務の効率化や安定稼働の実現、DX化の推進や課題の改善にお役立てください。