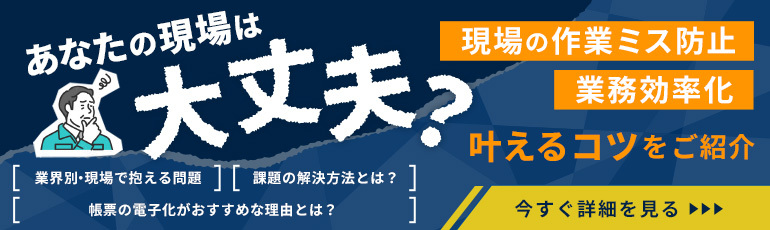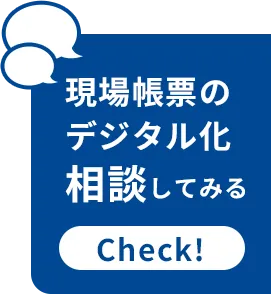目次
食品への異物混入は、企業の信頼を大きく損なうだけでなく、消費者の健康を害する可能性もある大きな問題です。
近年では、SNSでの拡散も容易になり、一度問題が発生すると、その影響は計り知れません。
特に、健康被害に繋がるような事態が発生した場合、企業イメージの低下は避けられず、最悪の場合は事業継続が困難になることも考えられます。
「まさか自分のところでは…」と思っている経営者の方も、決して他人事ではありません。特に、原材料の価格高騰などでコスト削減を迫られている状況下では、品質管理体制への影響も懸念されます。
作業者の教育を徹底し、異物混入の予防策を講じることが重要です。また、自主回収のプロセスや、異物混入の状態を把握し、効果的な解決策として外部の専門家の意見を取り入れることが求められるでしょう。
この記事では、食品業界における異物混入の現状をデータに基づいて解説し、製造現場で発生する主な原因、そして効果的な防止対策について徹底解説します。
製品の回収やプラスチック製品の混入防止策としての装置の導入、そして継続的な改善活動の必要性についても触れますので、企業が確実に対応できる方法を提案し、異物混入に対する判断力を高めるためにご活用ください。
食品への異物混入が多いものは?
食品への異物混入は、消費者の信頼を揺るがす深刻な問題です。
近年では、飲食店だけでなく、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで購入した食品からのクレームも増加傾向にあります。このような事態においては、迅速かつ適切なクレーム対応、そしてお詫びと原因究明が重要です。
厚生労働科学研究の調査によると、平成28年12月から令和元年7月までの3年間に、150の自治体で扱われた苦情処理事例は14684件に及びます。
その中には、プラスチックや金属片、さらには昆虫など、さまざまな異物が含まれており、このような異物混入は、特に健康被害に繋がる危険性があり、企業の責任は非常に重いと言えるでしょう。
企業が取るべき解決策としては、まず作業者の教育を徹底することが挙げられます。また、自主回収や迅速な情報発信も、消費者の信頼を保持するために欠かせません。
1位:虫
異物混入の第1位は、全体の約4分の1(23.9%)を占める「虫」です。
ハエやゴキブリといった比較的大型の虫だけでなく、肉眼では確認しづらい虫卵や幼虫、蛹なども含まれます。
これらの虫は、食品の製造過程や保管中に、工場の隙間や換気口から侵入したり、原材料に付着して持ち込まれたりするケースが多いのが特徴です。
2位:合成樹脂類
2番目に多いのは、「合成樹脂類」で全体に占める割合は17.5%になります。
ビニールやゴムなどが該当し、包装材や製造に使用する器具の破損が原因となることが多いです。
特に、食品と直接触れる部分に使用されている素材が劣化すると、破片が混入するリスクが高まります。
3位:動物性異物
3位は「動物性異物」です。全体に占める割合としては17%で人毛や獣毛、稀に人の歯などが混入する事例も報告されています。
作業員の衛生管理の不徹底や、工場内に動物が侵入してしまうことが主な原因です。
4位:鉱物性異物
「鉱物性異物」で、金属、ガラス、石、砂などが該当し全体に占める割合は15.9%です。
特に金属製の異物(ネジや金属片など)は、異物検出機で発見できる可能性が高いですが、発見できないほど微細なものもあります。
製造設備の破損や不適切な取り扱いが原因となることが多く、特に金属片は、機械の摩耗や破損から発生するケースが見られることから、製造ラインにおけるマグネットの設置、そして定期的な洗浄が効果的です。
5位:寄生虫
5位は全体の2.8%で「寄生虫」です。アニサキスなどの寄生虫が混入する事例が報告されています。
アニサキスは、海産魚介類に寄生する線虫の一種です。生きたまま摂取すると激しい腹痛を引き起こすことがあります。
6位:その他
その他として、全体に占める割合は23.1%で植物性異物、紙、繊維、たばこ、絆創膏、食品の一部などが挙げられます。これらの異物は、原材料の段階で混入していることもあり、注意が必要です。
【出典】「全国における食品への異物混入被害実態の把握(平成 28 年 12 月~令和元年 7 月)」(厚生労働科学研究成果データベース)
製造現場で異物が混入する主な原因
異物混入は、単一の原因で発生するものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生することが多いです。
ここでは、製造現場で異物が混入する主な原因について、詳しく解説していきます。
施設・設備の不備
施設・設備の不備は異物混入の大きな原因です。
老朽化した設備の破損による欠片、使用器具の部品脱落、フィルターの劣化、掲示物の剥がれなどがリスクを高めます。
特に、老朽化による破損や、器具の不具合、フィルターの機能低下は、直接製品に影響を及ぼす可能性があり注意が必要です。
適切な設備点検とメンテナンスを怠ると、これらのリスクは増大し、製品の品質低下や安全性の問題につながるため、定期的な点検とメンテナンスが重要になります。
従業員の衛生管理不足
従業員の衛生管理不足は、異物混入の重大な原因の一つです。
髪の毛、爪、制服からの繊維くずの混入、不適切なヘアキャップ着用などが考えられます。手洗いの不徹底も、細菌汚染や異物混入につながるでしょう。
製造工程に入る前の粘着ローラーの使用を徹底することで、衣服に付着した異物を除去することがポイントです。
手袋や作業着の不適切な使用、例えば破損した手袋の使用や作業着の汚れ放置も同様になります。
これらの衛生管理不足は、製品の品質を損ない、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性もあるため、徹底した衛生教育と管理体制の構築が大切です。
害虫や小動物の侵入
害虫や小動物の侵入は、深刻な異物混入リスクです。工場の隙間や亀裂からの侵入に加え、飛来する虫や歩行性の虫、何かに付着して侵入するケースも考えられます。
これらは製品に直接混入するだけでなく、細菌や病原菌を媒介する可能性もあり、衛生環境を著しく悪化させる原因です。
施設の立地条件や清掃不足は、害虫の繁殖を招き、侵入リスクを高めます。定期的な駆除、侵入経路の遮断、徹底した清掃が重要となります。
原材料の管理不足
原材料の管理不足は、異物混入の根本的な原因です。カビやホコリの発生、昆虫や幼虫の混入などが考えられます。
これらは、輸送や保管時の温度管理や湿度管理が不十分な場合、カビの繁殖や害虫の発生を招き、異物混入のリスクは更に高まるでしょう。
原材料の調達から保管、使用までの全工程で、適切な管理と定期的なチェックが重要です。
人為的なミス
作業中の不注意や手順の不遵守は、異物混入の直接的な原因です。
包装材や道具の破損に気付かず使用する、異物の混入に繋がる可能性のある行動を見過ごす、あるいは定められた作業手順を無視するなどが該当します。
徹底した作業手順の遵守、注意喚起の強化、従業員の意識向上、そして、無理のない作業工程の確立が、異物混入を防ぐ上で重要です。
異物混入を防ぐために製造現場でできる対策とは
異物混入を防ぐためには、「入れない」「持ち込まない」「取り除く」という3原則に基づいた対策が重要です。
ここでは、これらの原則に基づき、製造現場でできる具体的な対策について解説します。
施設や設備の管理を見直す
加工機械や設備の定期点検を実施し、摩耗や破損部分を早期に修理することが重要です。点検記録を詳細に残し、改善に繋げましょう。
食品加工エリア内の適切な洗浄を徹底し、異物の発生を防止することも大切になります。洗浄に使用する洗剤や機器の選定も重要です。
また、異物を検出する金属探知機など機器の導入も検討しましょう。
従業員の衛生教育を行う
作業員に定期的な衛生管理トレーニングを実施し、異物混入リスクの意識を高めることが重要です。
トレーニング内容を定期的に見直し、毛髪や繊維の混入を防ぐため、適切なユニフォーム(帽子、マスクなど)の着用を指導しましょう。
また、作業区域での私物持ち込みを制限することも有効です。
害虫や小動物の侵入防止策を講じる
工場や倉庫の周辺環境を清掃し、害虫や小動物が住み着かない環境を整備することが重要です。
定期的に害虫駆除を行い、侵入経路となる隙間をふさぎ、虫を引き寄せる要因となる原材料の保管環境を適切に管理することも意識しましょう。
原材料や製品の検査・管理方法を見直す
原材料の受け入れ時に異物混入の有無を検品し、問題があれば調達元に報告することが重要です。検査方法を標準化し、記録を残すことをおすすめします。
また、保管中に異物が混入しないよう、密閉された容器や適切な温度・湿度での管理や製品の最終検査工程で異物の混入がないかチェックも徹底しましょう。
標準作業手順を整備する
作業手順を明確にし、従業員が正しく作業を行う体制を構築することが重要です。
定期的に作業工程を見直し、新しいリスクに対応可能な体制を整備しましょう。作業手順書やマニュアルの作成が効果的です。手順書は、写真やイラストを多く使用し、誰でも理解しやすいように作成すると効果的です。
異物混入対策と効率的な商品回転率向上のためのデジタル化
異物混入や不正行為は、消費者の健康被害の原因になるだけではなく、企業の信頼低下や経済的損失といったリスクを引き起こします。
そのため、帳票やチェックシートの電子化により、情報共有の迅速化や記録ミスの軽減に貢献し、対策を効率的かつ効果的に強化することが重要です。
現場帳票システムi-Reporterなら、紙のレイアウトを保ったまま簡単に導入できます。誰でも簡単に操作でき、リアルタイムでのデータを共有・収集が可能です。さらに、オフライン環境や多言語にも対応しています。
i-Reporterを導入することで、異物混入対策を強化するだけでなく、業務効率化やコスト削減、品質向上など、さまざまな効果が期待できます。この機会に検討してみてはいかがでしょうか。