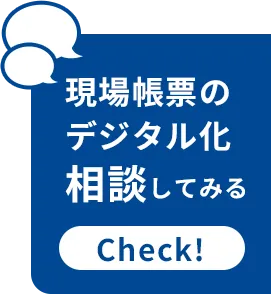製品検査とは?実施するメリットや注意点、効率化のポイント
目次
製造業において、製品検査は欠かせないプロセスです。 製品の品質を確保し、顧客からの信頼を得るために、適切な品質検査を実施することが求められます。
しかし、製品検査の目的や具体的な方法、効率化のポイントについて、十分に理解しているでしょうか?
この記事では、小売業や製造業の経営者、品質管理や生産管理の担当者に向けて、製品検査の基本から効率化のヒントまでを解説します。特に、衣料品や家庭用品、医薬品などの分野において、素材や生地、加工工程での不具合やミスをチェックすることは重要です。
製品検査を自動化し、業務効率を向上させたい企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
製造業の現場で行う製品検査とは?
製品検査は、製造業における品質管理の根幹をなす重要な工程です。
製品が設計通りに製造されているか、安全に使用できるかを確かめるために、さまざまな方法で検査が行われます。
ここでは、製品検査の定義や、関連する品質管理、品質保証との違いについて見ていきましょう。
正確な測定器を用いた試験により、製品の重量やサイズ、機能性などをチェックし、必要に応じて修正を行います。
これにより、不適合品やトラブルの発生を防ぎ、エンドユーザーに安心して使用できる商品を納品する仕組みが整います。また、法律やJIS規格に基づいた確認も不可欠です。
最終的には、これらのプロセスを通じて高い製品品質を担保し、顧客の信用を得ることが成果につながります。
製品検査とは
製品検査とは、製造された製品や部品が、あらかじめ定められた検査項目を含む品質基準を満たしているかどうかを確認するプロセスのことです。
製品や部品の寸法やキズの有無などを直接確認する作業であり、通常、工場の生産ラインや製品倉庫で実施されます。
製品検査の目的は、不備のある原料や資材を使用した不良品を市場に流出する前に発見し、排除することです。
不良品が消費者に渡ってしまうと、顧客からの信頼を失うだけでなく、企業のブランドイメージを損なうからです。
「製品検査」と「品質管理」や「品質保証」の違い
製品検査、品質管理、品質保証は、いずれも製品の品質を確保するための活動ですが、それぞれ異なる役割を持っています。
品質管理とは、製造工程全体の管理のことです。製品の設計段階から、原料の調達、製造、検査、出荷まで、一連のプロセス全体を管理し、品質向上させるための活動を指します。
例えば、統計的工程管理(Statistical Process Control: SPC)を用いて、製造プロセスの変動を監視し、異常が発生した場合に迅速に対応する、といった事例が挙げられるでしょう。
一方、品質保証は、顧客の期待に応えるための活動です。製品の品質を保証するために、企業が実施するすべての活動を指し、品質管理活動だけではありません。
顧客からのフィードバックの収集や分析、クレーム対応なども含まれ、製品検査は品質管理の一部であり、品質保証を支える重要な要素の一つと言えます。
成功した製品の背景には、信頼性の高い品質管理体制と、厳格な製品検査の流れがあると言えるでしょう。
これにより、エンドユーザーに安心して着用できる商品を納品することが可能になります。製造業での品質向上のためには、これらの活動が相互に関連し、効率的に進められることが求められるでしょう。
製品検査の種類や実施方法
製品検査の方法は多岐に渡り、検査の目的や対象製品によって異なります。
製品の種類や製造プロセスに応じて適切な方法を選択し、組み合わせることが重要です。
検査のタイミングには、受入検査、工程内検査、出荷検査などがあり、それぞれの段階で異なる目的があります。
受入検査では、原材料や部品が規定通りであるか確認し、工程内検査では製造過程中に発生する不具合を早期に検出・修正が可能です。出荷検査では、最終製品が顧客の期待に応える品質であるか最終確認を行います。
また、検査の種類には視覚検査、寸法測定、機能試験、微生物検査などがあり、例えば、衣料品の場合、縫製や生地のチェックが重要になります。一方、医薬品では、温度管理や成分分析といった試験が欠かせません。
これらの検査手法を適切に選択し、必要に応じて活用することで、高品質な製品の提供に繋がります。
ここからは、製品検査のタイミングや種類、実施方法についてみていきましょう。
主な検査のタイミング
製品検査は、その実施タイミングによっていくつかの種類に分けられます。 まず、これらが事前に定められた品質基準を満たしているかを確認しましょう。
この検査によって不良品の混入を防ぎ、後工程での問題発生を未然に防ぐことが可能となります。
次に行う工程は、製造現場の製造ライン上で行われる検査です。製造途中の製品に不備がないかを確認し、出荷検査(最終検査)は、完成品に対して行われる最終的な確認となります。
主な検査の種類
製品検査には、主なものとして外観検査、機能検査、官能検査の3種類があります。
外観検査では、目視やカメラ、検査装置、画像センサーなどを用いて、製品にキズやへこみ、汚れがないかを確認します。
例えば、自動車の外装に傷がないか確認するための目視検査や、スマートフォンの画面に気泡や傷がないかをチェックする方法が挙げられ、製品の外観や外装の品質を確保するために重要です。
機能検査は、製品が正しく動作するか、性能が求められている基準を満たしているかを確認するプロセスです。例えば、家電製品では、冷蔵庫の庫内温度が設定通りに保たれるかのテストや、洗濯機が所定の洗濯モードで正常に動作するか検証することがあります。
この検査により、製品の実際の使用における信頼性が確保されるでしょう。
官能検査は、人間の五感(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)を活用して行われる検査方法です。
特に食品や香料など、感覚的な特性が求められる製品において、その品質を評価します。
例えば、コーヒーの官能評価では香りや味のバランスを専門のパネリストが評価することや、化粧品でのテクスチャーや吸収感を確認するための触覚検査などが行われます。
これらの検査は、製品の品質を多角的に評価し、顧客に信頼される製品を提供するために欠かせない要素です。
主な検査の実施方法
製品検査には主に2つの方法があります。
ひとつは全数検査であり、これは製造されたすべての製品を個別に検査する手法です。
この方法のメリットは、全ての製品が基準に適合しているかどうかを厳密に確認できるため、品質保証の精度が非常に高い点ですが、デメリットとしては、検査にかかる時間とコストが大きくなりがちなことがあります。
もうひとつは抜き取り検査です。この方法では、製品ロットから一部のサンプルを抽出して検査を行います。
抜き取り検査のメリットは、全数検査に比べて時間とコストを抑えつつ、一定の品質を確保できるため効率的だという点です。デメリットとしては、少数のサンプルに基づいて判断するため、不良品の見落としリスクがあります。
どちらの検査方法も、製品の品質管理において重要な役割を果たしています。
製品検査を行うメリットと注意点
製品検査は、安定した品質を維持し、不良の原因を特定して品質向上につなげることができるでしょう。
一方で、検査基準の不明確さやヒューマンエラーなど、注意すべき点もあります。ここでは、製品検査を行うメリットと注意点について見ていきましょう。
製品検査を行うメリット
製品検査には以下のようなメリットがあります。
• 安定した品質を維持し、不良の原因を特定して品質向上につなげることができる
• 製造段階で不備を見つけ出し、不良品の流出を防げる
• 生産性の向上や製品の信頼性向上が期待できる
• 顧客や取引先からの信頼を高める
• 消費者の満足度向上に貢献
安定した品質を維持することで、不良品の原因を特定し、品質向上に繋げることが可能です。
また、製造段階で不備を早期に発見することで、不良品の流出を防ぐことができるでしょう。
これにより、生産性の向上や製品の信頼性が期待でき、結果として顧客や取引先からの信頼を高めることに繋がります。消費者の満足度向上に寄与することができるでしょう
製品検査を行う注意点
一方で、製品検査を行う際には以下の様な注意点も存在します。
• 検査項目を含む検査基準の明確にする
• ヒューマンエラーのリスクを考慮する
• コストと検査精度のバランスを見極める必要がある
製品検査を行う注意点として、検査項目を含む検査基準を明確にすることが重要です。
不明確な基準では、検査結果が一貫性を欠く可能性があり、ヒューマンエラーのリスクも念頭に置く必要があります。
作業員の経験や疲労度によって、検査結果にばらつきが生じることがあるため注意が必要です。
さらに、コストと検査精度のバランスを見極めることも重要になります。過剰なコストを検査にかけると、企業の収益を圧迫する可能性があるため、慎重に考慮する必要があるでしょう。
製品検査を効率化するポイント
製品の特性や生産規模に応じて、最適な検査方法を選択することが大切です。
自動化やDXを推進し、検査工程を適切化することで、製品検査を効率化できます。ここでは、製品検査を効率化するポイントについて解説します。
自動化とデジタル化の推進
検査精度向上と時間短縮のため、画像処理、センサー測定、自動計測システムの構築などを検討しましょう。
AIを活用することで、より高度な検査も実現可能になります。 帳票やチェックシートの電子化や検査データのデジタル化も効果的です。
帳票やチェックシートを電子化するメリットは多岐にわたります。 紙の帳票に比べて、データの入力や集計作業が大幅に業務効率化されるでしょう。
電子化されたデータは、リアルタイムで共有できるため、関係者間での情報共有がスムーズになり、紙の帳票のように紛失や破損の心配がなく、長期的な保存にも適しており、コスト削減にも繋がります。
検査工程の適切化
ヒューマンエラーや作業の属人化を防ぐため、検査マニュアルの共有やフローチャートの活用などを検討しましょう。 検査工程の見える化や標準化を目指すことが重要です。
明確な検査基準の設定
検査項目を含む検査の判断基準を統一し、作業員による判断のばらつきを抑えるため、数値的な基準を設定しましょう。
グレーゾーンについても、具体的な判定基準を設けることが重要です。 品質表示についても、明確な基準を設けることが求められます。
検査環境の整備
不良品のキズなどの見逃しを防ぐため、適切な照明や作業スペースの確保などを徹底しましょう。
製品検査のさらなる進化へ「i-Reporter」で実現する検査業務のデジタル化
この記事では、製造業における品質検査の重要性と基本的な方法について解説しました。
品質検査は、製品が設計通りに製造されているか、安全性が確保されているかを確認し、不良品の流出を防ぐ役割があります。
品質向上や効率化にはDXの推進が欠かせません。使い慣れたExcel帳票の帳票や検査チェックシートを電子化するなら「i-Reporter」がおすすめです。
i-Reporterは、既存のExcelの入力フォーマットを比較的簡単に再現でき、システムに詳しくない管理者でも運用管理がしやすいでしょう。データ抽出やデータ連携などによって、コスト削減や業務効率化も期待できます。
i-Reporterを活用することで、検査データのリアルタイムな共有やデータ分析による傾向把握、迅速な改善策の実施が可能になります。
ぜひ、製品検査のDXを推進しにi-Reporterの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
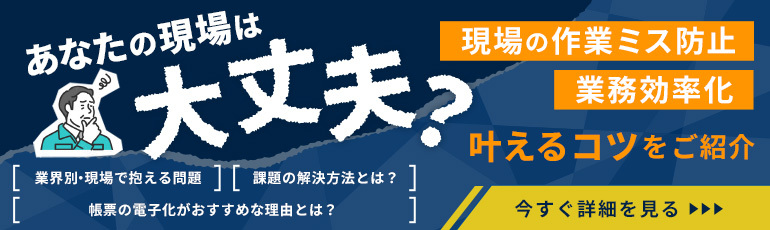

現場帳票研究所の編集部です!
当ブログは現場帳票電子化ソリューション「i-Reporter」の開発・販売を行う株式会社シムトップスが運営しております。
現場DXの推進に奮闘する皆様のお役に立てるよう、業界情報を定期的に配信致しますので、ぜひ御覧ください!