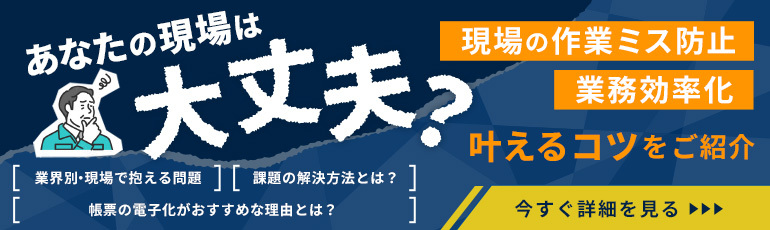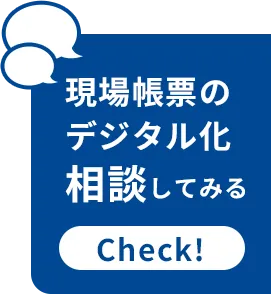7つのムダとは?覚え方、ムダの具体例と現場でのチェックポイント
目次
製造業の現場では、日々の業務の中で、効率の悪さや不良品の発生、余計なコストに頭を悩ませることが少なくありません。このような課題を解決するための鍵となるのが、トヨタ生産方式における「7つのムダ」という考え方です。7つのムダを理解することで、現場に潜む非効率なプロセスやリソースの浪費を洗い出し、具体的な改善手法を検討することが可能になります。本記事では、7つのムダの定義や具体例を紹介するとともに、現場で役立つチェックシートや、ムダを可視化するポイントについてくわしく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
7つのムダとは?
製造現場での効率化や企業の生産性向上を実現するために、まず目を向けるべき重要な視点があります。それが、トヨタ生産方式において特定された、「7つのムダ」という概念です。7つのムダとは、生産プロセスにおけるさまざまな無駄や非効率な要素を指し、仕事や作業の中に潜む「ムダ(=効率を悪くするもの)」を7つの種類に分類したものです。
これらのムダを減らす取り組みは、業務効率の向上やコスト削減に直結します。7つのムダの概要と、背景にあるトヨタ生産方式の考え方の詳細をご説明します。
7つのムダの覚え方
製造現場におけるムダを明確に理解し、チーム全体で共有するためには、まずは7つのムダを正確に覚える必要があります。その際に役立つのが、語呂合わせによる覚え方です。
最も有名なのが、「飾って豆腐(かざってとうふ・かざってどうふ)」というフレーズです。それぞれ以下の頭文字を意味します。
か:加工(かこう)のムダ
ざ:在庫(ざいこ)のムダ
っ(て):手待ち(てまち)のムダ
て:手直し(てなおし)のムダ
と:動作(どうさ)のムダ
う:運搬(うんぱん)のムダ
ふ:不良(ふりょう)のムダ
ムダを体系的に認識しやすくすることで、現場改善に向けた現状把握や業務改善の第一歩を踏み出しやすくなります。
そもそも「トヨタ生産方式」とは
7つのムダという考え方の根底にあるのが、トヨタ自動車が長年の試行錯誤の末に確立した、生産管理手法の「トヨタ生産方式(TPS:Toyota Production System)」です。TPSは、「ジャスト・イン・タイム(JIT)」と「自働化」という2つの柱を中心に、徹底的なムダの排除と品質向上を目指しています。
「ジャスト・イン・タイム」は、「必要なものを、必要なときに、必要な量だけ」生産・供給するという考え方で、過剰な在庫や仕掛品の発生を抑止します。一方、「自働化」は、単なる自動化とは違い、異常が発生した際に機械が自動的に停止し、不良品を未然に防ぐ仕組みです。「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」という基本思想を、製造のすべての工程で徹底することでムダをなくし、より効率的な生産体制を実現しています。
トヨタ生産方式では、「ムダを見つけ、取り除くことが最大の改善手法」とされており、その考え方を具体的に分類・整理したのが7つのムダなのです。例えば、作業手順が標準化されていなかったり、DXによる可視化が不十分だったりする現場では、非効率な業務が繰り返され、生産性の低下や人件費の損失を招く恐れがあるでしょう。
トヨタ生産方式の思想を理解することは、単なる生産現場の改善だけでなく、企業全体の競争力強化にも直結するため、7つのムダの視点を持つことは非常に重要といえます。
7つのムダの具体例と現場でのチェックシート
7つのムダを理解しているつもりでも、製造現場で実際にどのようなケースが該当するのかを把握できていないと、業務改善やムダ取りにはつながりません。ムダは一見すると正当な作業のように見えがちですが、日常業務に深く入り込んでおり、作業効率や生産性の低下、工数の増加や人件費のムダといった大きな損失を招きます。
7つのムダに分類されるそれぞれの要素について、現場でよくある事例やチェックすべきポイントをご説明します。
1.加工のムダ
加工のムダとは、必要以上に手を加えることで起こるムダを指しており、製品の品質や機能に直接関係しない加工を過剰に行うことです。例えば、顧客が注文していない装飾や、工程上必要のない仕上げ作業の追加などが該当します。
また、作業手順が標準化されていないために、作業員によって加工の度合いにばらつきが生じることも、加工のムダにつながります。
| 【現場のチェックポイント】 ・その作業を本当に顧客が求めているか? ・機能に直結しない加工が含まれていないか? ・標準作業に含まれていない作業が、いつの間にか習慣化されていないか? |
加工のムダは、工数の増加を招くだけでなく、原材料の浪費や品質のばらつきを引き起こす要因にもなります。
2.在庫のムダ
在庫のムダは、必要以上に原材料や部品、仕掛品や完成品を抱えてしまうことで生じるムダです。商品の過剰在庫は、保管コストやスペースがムダになるだけではなく、在庫管理を行う人員の増加や廃棄リスクの増大など、さまざまな損失につながります。
| 【現場のチェックポイント】 ・在庫の回転率は適正か? ・不要な在庫が棚や床を占有していないか? ・倉庫の整理整頓はできているか?(5Sが徹底されているか) |
在庫の適正化を図るためには、綿密な生産計画や在庫管理が求められます。例えば、AIやDXツールによる在庫の可視化は、在庫のムダの解消に効果的です。また、生産管理システムやかんばん方式の導入もおすすめします。
3.動作のムダ
動作のムダとは、作業者が製品を造り上げる過程で発生する、付加価値を生まない余計な動きのことです。例えば、工具や部品を取りに行くために何度も歩いたり、不自然な姿勢での作業を強いられたりするケースが該当します。
工場内の非効率なレイアウトや、整理整頓されていない作業環境が、従業員の無駄な手間や移動を増やし、結果的に作業効率の低下を招きます。
| 【現場のチェックポイント】 ・必要な道具や資料がすぐ手に取れる場所にあるか? ・手や身体の動作に無駄な反復がないか? ・作業手順が標準化されておらず、動きが人によってバラバラになっていないか? |
レイアウトや道具配置の見直しを実践することで、作業時間を最小限に短縮できます。また、図面や動画を活用した作業分析も改善に効果的です。
4.作りすぎのムダ
作りすぎのムダは、必要以上の量を生産することで発生するムダです。見込み生産や予測のズレにより、完成品や仕掛品が過剰になると、検査の手間や保管場所の確保、品質低下による廃棄などの問題が発生します。
| 【現場のチェックポイント】 ・「念のため」で余分に生産していないか? ・顧客の実際の需要と生産計画にズレがないか? ・「とりあえず多めに作る」が習慣化していないか? |
「ジャスト・イン・タイム」の考え方に基づき、「必要な時に、必要な量だけ」生産する体制を構築することが重要です。
5.手待ちのムダ
手待ちのムダとは、作業員や機械が何もせずに待機している時間です。例えば、前工程の遅れや設備の故障、材料が届かないといった理由で、後工程が止まっている状態が挙げられます。
| 【現場のチェックポイント】 ・待ち時間が発生していないか? ・段取り替えなどの準備時間が長すぎないか? ・スケジューリングや部品供給の遅延が頻発していないか? |
手待ち時間は生産性の低下に直結し、人件費や設備稼働率の低下といった損失を生み出すでしょう。生産スケジュールや段取り作業の標準化、設備保全の徹底が求められます。
6.運搬のムダ
運搬のムダとは、部品や資料を移動する時間や距離がムダになっている状態を指します。「持っていく」「探す」といった行為は、製品に付加価値を生み出す行為ではありません。特に、移動距離が長い、何度も同じものを運んでいるといった状態は、ムダの温床になります。
| 【現場のチェックポイント】 ・作業エリアの配置は効率的か? ・何度も同じ物を移動していないか? ・移動ルートやレイアウトが複雑で遠回りになっていないか? |
工場内の非効率なレイアウトや保管場所の分散、不適切な搬送方法などが、運搬のムダを増大させる要因となります。従来の工場全体のレイアウトを見直し、物の流れを最適化することが重要です。
7.不良・手直しのムダ
7つのムダの中で最も損失が大きいのが、不良・手直しのムダです。不良・手直しのムダとは、製造された製品の品質に不備があり、再加工や修正が必要になることで発生するムダを指します。
不良品の発生は、材料費や人件費、時間を浪費するだけでなく、顧客からの信頼を失う可能性もあります。
| 【現場のチェックポイント】 ・ミスの原因が工程に潜んでいないか? ・修正ややり直しが頻繁に発生していないか? ・不良が出た原因分析や再発防止を行っているか? |
不良の原因を徹底的に追究し、再発防止のための品質管理体制を強化することが不可欠です。検査体制の見直しや作業標準の設定、自動化による品質の安定化も、有効な改善手法となります。
7つのムダを可視化するポイント
7つのムダは、業種や規模を問わず、あらゆる製造現場に潜んでいます。しかし、その存在の多くが「目に見えない=気づけない」ものであるため、ムダの見つけ方がわからず、現場改善の対策が進められないまま、放置されているケースも少なくありません。
このような状況を改善するためには、ムダを「見える化」し、全体で共有・意識できる環境を作ることが重要です。7つのムダを可視化するための、進め方のヒントをご紹介します。
①どこに「価値がない動き」があるかを洗い出す
ムダを可視化する最初のステップは、日々の作業の流れを細かく分解し、それぞれの工程が顧客にとって本当に価値を生み出しているのかどうかという視点で見直すことです。
例えば、部品や資料の運搬や機械の手待ち時間、作業手順の確認作業などの動きが付加価値を生んでいない場合は、改善の対象となります。価値がない動きを特定することが、作業の無駄を削減し、生産性向上につなげる第一歩です。
②データとして残す
その場で気づいたムダも、記録しなければ改善活動に活かせないため、データとして残すことも重要なポイントです。口頭での報告だけではムダの本質が伝わらず、同じ問題が再発するリスクも高まります。
そのため、帳票システムや在庫管理システムなどを活用し、ムダが発生した箇所や頻度などを、データとして記録することが欠かせません。ムダの発生傾向を継続的に分析できる状態を作り出すことで、より効果的な対処法や改善手法を検討できるでしょう。
③チーム全員で共有できる仕組みをつくる
ムダに気づいた個人だけが改善を進めても、現場全体の効率化にはつながりません。「どこにムダがあるのか」「なぜ起きたのか」という情報を、管理者だけではなく誰でも見える状態にすることが大切です。
例えば、ムダの内容と改善策を共有する朝礼の実施や、誰でも気軽に意見を記入・閲覧できるデジタルツールの導入などが有効です。
7つのムダを見える化!「i-Reporter」で現場改善を加速
製造現場におけるムダの排除は、生産性向上やコスト削減、品質改善を実現するための重要な取り組みです。加工・在庫・手待ち・手直し・動作・運搬・不良という7つの観点からムダを見直すことで、企業全体の生産効率向上につながります。
ムダの「見える化」と継続的な業務改善には、現場帳票システム「i-Reporter」が有効です。「i-Reporter」は、紙での作業記録を電子化し、現場の情報をリアルタイムで蓄積・分析することで、ムダの発見から改善までを支援します。
また、タブレット入力ですぐに情報を共有でき、工程ごとの記録も一覧で確認できるため、異常値やムダの「見える化」が可能です。さらに、改善結果も記録として蓄積されるため、継続的なカイゼンに活用できるメリットもあります。
7つのムダを意識した現場改善に「i-Reporter」を活用すれば、生産性向上と効率化を同時に実現し、持続可能なものづくりの未来を築けるでしょう。