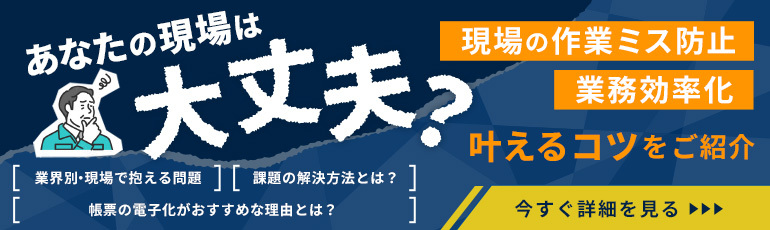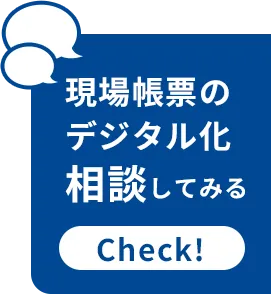実技実習生を取り巻く問題とは?企業が解決に向けて取るべき行動
目次
技能実習生制度は、発展途上国への技術移転を目的とした日本の重要な制度ですが、同時に多くの課題を抱えています。低賃金や長時間労働、人権侵害といった問題は、技能実習生の権利を脅かすだけでなく、企業の信頼性にも大きな影響を与えるため、注意が必要です。
ここでは、技能実習生が抱える問題から、企業が取り組むべき対策や解決策までくわしく解説します。技能実習生が安心して働ける環境を整え、企業にとっても有益な関係を築くために、ぜひお役立てください。
技能実習生とは?技能実習制度の概要
技能実習生とは、技能実習制度を通じて日本で就労する外国人のことです。この教育制度は、1993年に導入され、発展途上国への技術移転を目的としています。
令和4年末時点で、全国には約32万人の外国人技能実習生が在留しており、農業や食品製造など、対象となるさまざまな産業や分野で働いています。
技能実習制度の目的
技能実習制度は、主に発展途上国からの人材を受け入れ、日本の高度な技能や技術を学ばせることが目的です。技能実習法の要件に基づき、最長5年間の在留期間が認められており、滞在中に習得した知識やスキルを自国に持ち帰り、母国の発展に貢献することが期待されています。
技能実習生の受け入れ方法
技能実習生の受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。
企業単独型は、日本の受入れ企業が、海外の現地法人や取引先などの密接な関係のある企業から、技能実習生を直接受け入れる方法です。一方、団体監理型は、事業協同組合や商工会などの非営利団体(監理団体)が仲介し、技能実習生を受け入れる方法です。受け入れた技能実習生に対し、監理団体の傘下の企業などで技能実習を行います。
令和4年末時点では、技能実習生の受け入れの98.3%は団体監理型です。このことから、中小企業が技能実習生を受け入れるには、監理団体のサポートが不可欠であることがわかります。
技能実習生の受け入れが多い職種
外国人採用が多い職種は、建設関係や食品製造関係、機械・金属関係です。特に、建設現場や食品製造の実習先では、多くの技能実習生が重要な役割を果たしています。
その次に多いのが、農業関係です。ほかにも、繊維・衣服関係や漁業関係など、受け入れ企業はさまざまな業界に広がっており、労働者としての技能実習生は、日本にとって欠かせない存在となっています。
また、技能実習生の受け入れが多い国としては、ベトナム、インドネシア、フィリピンの順に多く、日本企業側もこれらの国々からの外国人材を、積極的に採用しています。
技能実習生の入国後の流れ
技能実習生が、日本に入国後にまず行うのが、法務省が定める在留資格に基づいて、外国人として日本で生活するための手続きです。その後、日本語教育や法的保護に関する講習を受けることから始めます。この講習は、技能実習生が日本での生活や労働に必要な基本知識を習得し、安心して仕事に取り組むための重要なプロセスです。
講習後は、実習実施者との雇用関係のもとで、現場で実習を開始します。技能実習計画に基づいて、実践的な技能等の修得や習熟を図りながら、日本の現場での作業に従事し、対象分野や対象職種における必要なスキルを身につけます。
【出展】「外国人技能実習制度の現状と課題」 (厚生労働省)
技能実習生を取り巻く主な問題
技能実習制度は、日本の労働力を支える重要な制度ですが、さまざまな問題点も抱えています。べトナム人の技能実習生による犯罪や失踪など、技能実習生に関するニュースを耳にしたことがあるでしょう。
技能実習生を取り巻く主な問題をご紹介します。
長時間労働
最も問題視されているのが、長時間労働です。受け入れ企業によっては、残業が常態化しており、過労による健康被害が懸念されています。過酷な長時間労働の強要により、心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
賃金の支払いに関する問題
賃金の支払いに関する問題も深刻です。給料や残業代の未払いや、最低賃金以下での雇用などが挙げられます。
なかには、時間外労働の単価が1時間当たり500円程度しか支払われなかった事例もあり、技能実習生の生活を圧迫し、不安を増大させる原因となっているのが現状です。
【参考】 「外国人技能実習制度の現状と課題」 (厚生労働省)
労働災害
技能実習生の労働災害は、年間約500件にものぼります。建設業や製造業など、労災リスクの高い業種で多く働いていることも原因の1つです。
【参考】 「技能実習生の労働災害を防止しましょう」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
人権侵害
暴言・暴力や不当な扱い、パワハラやセクハラといったハラスメントなど、さまざまな人権侵害行為が報告されています。これらの悪質な不正行為により、技能実習生が精神的なストレスやトラウマを抱えることも少なくありません。
失踪問題
技能実習中に失踪する外国人は増加傾向にあり、2023年には過去最多の9,753人が失踪しました。背景には、違法な低賃金や長時間労働といった劣悪な労働環境や、人権侵害や転籍・転職できない問題など、さまざまな要因があります。
失踪した技能実習生は、不法就労や犯罪に巻き込まれるリスクも高まります。
【参考】 「技能実習生の失踪者の状況 ( 推 移 )」(出入国在留管理庁)
犯罪への関与
一部の技能実習生が、犯罪に巻き込まれるケースも報告されています。例えば、銀行口座の譲渡や不正送金への加担など、アルバイト感覚で自覚がないまま、犯罪に関与してしまうケースも少なくありません。
近隣とのトラブル
近隣とのトラブルも、技能実習生が抱える問題の一つです。技能実習生は、日本の生活習慣やルールに不慣れなことが多く、近隣住民とトラブルになることがあります。
例えば、ゴミの分別方法などの基本ルールを知らなかったり、騒音に関する認識に違いがあったりして、住民との間に摩擦が生じることが指摘されています。
技能実習生に関する問題が発生する主な原因
技能実習生に関する問題が発生する背景には、複合的な要因が存在します。
言語の壁や文化的な違い
技能実習生が日本で生活し、仕事をするうえで、言語の壁は大きな課題です。日本語を十分に理解できない場合、労働条件や作業内容、安全指導の内容が正しく伝わらないことがあります。例えば、指示の誤解や、現場でのトラブル発生などが考えられるでしょう。
また、日本独自の労働習慣や生活習慣を理解するのにも時間がかかり、職場や地域で誤解が生じやすい状況も生まれます。
経済的な困窮
技能実習生は、仲介業者にビザの取得などで多額の費用を徴収されるケースが多く、来日前に借金を背負っている技能実習生も珍しくありません。低賃金や不当な控除によって十分な収入を得られず、生活費や借金返済が困難になることもあります。
経済的プレッシャーから、技能実習生が不安になり、失踪や犯罪への加担へつながる可能性も高まるでしょう。
監理体制の不備
受け入れ企業や監理団体への指導が不十分な場合、違法行為が放置されることがあります。一部の監理団体や送り出し機関では、適切な指導やサポートが不足しているのが現状です。
また、技能実習生が被害を訴える場も限られており、問題が表面化しにくい構造的な課題も存在します。
受け入れ企業による法令違反
厚生労働省が発表した2023年の監督指導結果によると、監督指導が行われた実習実施者の事業場の73.3%で、労働基準関係法令の違反が確認されました。具体的には、安全基準を満たしていない機械や設備の使用、割増賃金の不適切な支払い、健康診断結果に基づく医師の意見聴取の不実施などが挙げられます。
企業側のコンプライアンス意識の低さが、問題発生の大きな要因です。
【参考】 「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況 」 (厚生労働省)
制度の矛盾
技能実習制度は本来、技能習得と国際貢献を目的とした制度ですが、実態は労働力不足を補う手段として利用されているケースがほとんどです。そのため、実習生の権利保護と企業のニーズの間で、バランスを取ることが難しい状況が続いています。
このような制度の矛盾に対応するため、政府によって新たな「育成就労」制度への移行が検討されています。技能実習制度の問題点・注意点の見直しや改善を行うことで、今後は外国人材の育成と定着のさらなる促進が期待できるでしょう。
【参考】 「育成就労制度の概要」 (出入国在留管理庁・厚生労働省)
企業ができる技能実習生問題の解決策
技能実習生の問題を解決するためには、企業の積極的な取り組みが必要です。企業ができる具体的な解決策をご説明します。
労働環境の整備
技能実習生が安心して働ける環境を整えることは、受け入れ企業の重要な責任です。安全管理や安全対策を徹底し、労働災害を未然に防ぐには、安全で衛生的な職場環境の確保が欠かせません。
また、労働時間や賃金などの労働条件は、日本人従業員と同様に設定し、差別的な扱いを避けることが重要です。住環境の整備も忘れず、安全で快適な住環境を提供することで、技能実習生の生活の質の向上につなげられます。
コミュニケーションの支援
技能実習生との円滑なコミュニケーションは、仕事の効率化だけでなく、相互理解を深める上でも不可欠です。日本語を十分に理解できない技能実習生に対しては、簡潔な表現やジェスチャーを積極的に活用しましょう。画像や図を使って説明すれば、業務内容や安全指示などを視覚的に理解できるようになります。
また、技能実習生が日常会話や業務に必要な表現を学べるように、日本語教育の機会を提供することも有効です。
教育や研修の充実
技能実習生が現場で活躍するためには、教育や研修の充実が欠かせません。技能実習の目的に沿った、専門的なスキル向上のための研修を実施し、技能実習生が帰国後に、母国で習得したスキルを活かせるよう支援します。
また、労働災害を防止するために、安全教育を徹底することが重要です。さらに、日本人従業員に対しても、異文化理解や適切な指導方法に関する研修を実施することで、技能実習生との良好な関係構築を促進できます。
コンプライアンスの強化
企業は法令遵守を徹底する必要があります。労働基準法や技能実習制度を正しく理解し、違法行為を未然に防がなくてはなりません。そのためには、定期的に社内監査を行い、不適切な行為が行われていないか確認することも重要です。
また、技能実習生が抱える不満や悩み、疑問を相談・面接しやすい仕組みを整えることで、問題が発生した際に早期解決が図れます。
文化理解の促進
社内で異文化交流の機会を提供することで、技能実習生と日本人従業員の相互理解が深まります。技能実習生の出身国の文化や習慣を尊重し、多様性を尊重する企業風土を構築することで、技能実習生との良好な関係を築けるでしょう。
技能実習生の問題解決に「i-Reporter」を活用しよう
技能実習生の受け入れには多くの課題が伴います。長時間労働の管理や言語の壁による誤解、指導の負担など、さまざまな問題が生じるでしょう。現場帳票システムの「i-Reporter」は、これらの問題を解決し、適正な労働環境を整え、業務効率の向上をサポートします。
「i-Reporter」を導入し、作業時間をリアルタイムでデジタル記録することで、長時間労働を未然に防止できます。また、日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)に対応しており、帳票レイアウトはExcelから作成できるため、タイ語やベトナム語など、各国言語での作成・入力が可能です。
「i-Reporter」は、技能実習生とのスムーズな意思疎通を促し、優良な企業として認定されるための強力なサポートツールとなりますので、ぜひ導入をご検討ください。