導入事例古河電気工業株式会社様
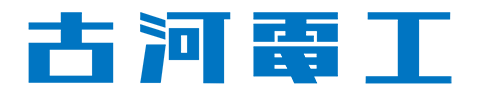
古河電気工業株式会社

製造ラインの記録の効率化事例
カイゼン効果
-
作業日誌や設備点検記録表が全て紙のためファイリングだけで毎月200分必要
-
月に200分を要していたファイリングが0分
-
帳票に年間約15,000枚の紙を使用するため保管スベースも膨大
-
年間15,000枚の帳票を保管していた管理スペースが不要
-
品質問題が発生した際、紙の帳票から情報整理が必要で原因解明に数日間必要
-
1帳票あたり20分かけていた帳票の検索時間も5分以内で確認可能
-

光ケーブル製造部 生産技術課 課長 松元 氏
-

光ケーブル製造部 部長 岡田 氏
-

光ケーブル製造部 製造課 渡部 氏
-

事業・プロセス変革チーム 松村 氏
-

光ケーブル製造部 生産技術課 上原 氏
-

光ケーブル製造部 生産技術課 竹内 氏
事例資料をダウンロードする
古河電気工業株式会社 導入事例資料古河電気工業株式会社(以下、古河電工)は、光ファイバ・電線・ワイヤーハーネス等の製造を行なう非鉄金属メーカー。
1884年に精銅・電線事業をスタートしてから培ってきた素材力・技術力を核に、さまざまな独自製品の開発に取り組んでいる。
時代を先取りしながら技術の裾野を広げ、社会インフラの発展に貢献している企業だ。

「以前は品質記録をすべて紙で保管し、エクセルへの転記を経て分析を行なっていました。
i-Reporterを利用し、記録する段階から電子化できたことで業務効率の改善につながりました。
特に、品質問題が発生してから、過去の品質記録の検索、原因の検出・分析のスピードが上がったことを体感しています。記録や集計スピードが上がった分、製造データのビジュアル化や分析に時間をかけられるようになったのも大きな価値です。」
日本・世界のインフラ発展に貢献
技術を開拓し続ける古河電工

「『世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間ない技術革新により、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。』
この基本理念を軸として、古河電工ではさまざまな独自製品を開発し、光ファイバなどの情報通信から、エネルギーインフラ、電装エレクトロニクスなど6つの事業分野で幅広い事業を展開しています。」
1960年代にはタイ・バンコクなどの東南アジアを始めとした海外へ進出。現在は遠くブラジルにまで製造工場を建設し、世界中で新しい技術や商品を生み出している。また、1978年から4年をかけてイランで大型送電線工事も手掛け、その技術で日本のみならず世界のインフラ発展に貢献してきた。
今回、製造工程管理にi-Reporterを導入した光ファイバ事業も、古河電工が手掛けてきた技術の一つだ。まだ光ファイバ草創期であった1974年に、古河電工は世界初の光ファイバケーブルのフィールド試験に成功した歴史を持つ。
現在は、日本の三重県、米国のジョージア州、インドのゴア州、ブラジルのサンパウロ州などに製造拠点を有しており、光ファイバと光ファイバケーブルを世界中へタイムリーに供給している。
膨大な量のデータを紙で記録・管理、
問題発生時の原因究明に時間と人手を要していた

「より良い製品を造るために、何より“現場”を大事にしています。アクシデントがあれば、まずは関係者が現場に赴いて確認作業をし、設備を止めて丁寧にチェックすることを心掛けています」
現物を見て現実を理解する「現場・現物・現実」の考え方を徹底している古河電工。日常的にフォロー会をおこない、設備や製造管理に異常がないかを現場の声として吸い上げている。
そんな同社の光ファイバケーブルの製造ラインでは、これまで品質記録として作業日誌や設備点検記録表をすべて紙に書いて保管していた。これらの書類は、分類毎にファイリングされ、必要に応じて情報を集計する流れだ。以前はファイリングだけで毎月200分はかかっていた、と渡部氏は話す。
集計するにも、データの大部分が手書きのため、まずはExcelなどへの転記が必要。また、分析したい内容によって集計するデータが異なるため、必要な情報をその都度転記して集計するという手間が掛かっていた。
「ファイリングから検索までに時間がかかり、膨大な紙の収容スペースも必要です。現場からも紙の使用量を減らせないか、というニーズは以前からありました」
帳票保管には年間でおよそ15,000枚の紙を使用していたため、その保管スペースも膨大なもの。そして、なかでも大きな課題だったのが、品質問題が発生した時だ。
問題が起きれば、もちろん原因を解明しなければならない。過去の製造履歴の情報を収集し、製造工程に問題が無いか検証する際、ファイリングされた紙の資料の中から該当データを探してExcelに集計し、グラフ化して情報を整理していた。
資料は現場で管理されているため、物理的に紙の帳票を移動させ、該当するものを探す。そこにかかっていた時間は相当なものだ。数名のメンバーが手分けして情報を整理して、会議を設けて分析、原因解明に至るまでのプロセスに数日間を要していた。
「品質問題が発生しているのに、数日間は対策を打てないのです。この部分の業務プロセスの効率の悪さが、一番解決したかった課題です」
また時を同じくして、社内ではIoT活用スマートファクトリー化に向けた業務プロセス改善に着手することに。きっかけは部全体で「ありたい姿」を言語化したことだった。
『設備の状態、材料、製品の品質を予知し、コンディションを自動調整するものづくり』
目標の一つにあった“予知”という言葉。さまざまなものを予知していかなければならない未来において、これまでのようにアナログで分析に時間をかけていては、その達成は難しい。「ありたい姿」に近づくための改善方法の一つにペーパーレス化、つまり管理工程の電子化があった。
「どこを電子化すべきか」
古河電工がここでも“現場”を選んだ理由
「紙から電子化へ」に取り組むにあたり、8名ほどのプロジェクトチームを作った。
まずは「どんな方法で製造データを取得するのが良いか」を検討するところから始まった。
製造ラインで記録を取る段階から帳票ソフトを活用し電子化するのか、またはこれまで通り製造ラインでは紙に記録を取り、紙に書かれた文字をスキャンしてデータに変換してデータベース化するのか。電子化がトレンドとなりつつあったこの頃には、各社にさまざまな電子化の方法があり、この2つが最終的な選択肢として残った。
IoT系の展示会に足を運びチームで検討を進めた結果、「現場での記録から電子化する」ことに決めた。

「必要なタイミングで必要な情報をすぐに吸い上げられることが重要でした。手書きの情報をデータ化するとなると、何かしら変換の工程を挟まなければいけない。
データ化するのであれば、すべての情報を一元化できるようにしておきたかったのです」
これまで慣れていた現場の動きを変えるのは、手間のかかる選択のようにも思える。しかし、ものづくりの要であり、設備や製品に対面している従業員から出る情報から電子化することで、集計や管理などの長い目で見れば効率がよいと考えた。
展示会でi-Reporterを知り、導入の決め手となったのもやはり“現場”。まずは「ユーザーである作業者が使いやすいかどうか」を基準に選んだ。
「まったく新しい記録用紙ではなく、これまで品質記録を書き留めていた用紙の内容をiPadに変換できるところがいいと思いました。入力作業が帳票ソフトに置き換わっても、同じスピード感、或いはより早く入力作業を完了できる。それが重要視していた点です」
紙とiPadという違いはあれど、以前使っていたものと似ているテンプレートを使用することで、ツール変更における現場の負担を軽減。作業に慣れてもらえさえすれば、以前よりも素早く入力できるようになると考えた。また、iPadであればファイリングされた紙よりも持ち運びやすく、現場で管理がしやすい。
使用感に加え、「紙から電子化」の先に「設備データの電子化」も見据えていた。それも、さまざまな情報を容易に融合させられるi-Reporterを導入した決め手の一つだ。
手厚いサポートで実用まで伴走
一部ではなくみんなが使えるソフト浸透を目指す
「ユーザーである従業員が使いやすいこと」を重視したとはいえ、これまでのやり方を変えるには、継続的なアプローチが必要だったと上原氏は振り返る。

「ソフト導入後にシムトップス主催の講習会を受講できたのが助かりました。プロジェクトメンバー8人中6人が参加し、基本的な操作スキルを学んできました。でも、ああいった講習会ではわかった気になって帰ってくるものの、実際に使用できるかは別です。間違える怖さもあり、なかなか実際の製造ラインへの導入には進めませんでした」
そこで役立ったのが、シムトップスが提供している「i-Reporter基本操作講習」のオンライン動画。不安なときや迷ったときには、二度、三度と繰り返し動画を見ながら操作を習得していった。
さらに、自社の品質記録用紙をiPad用のテンプレートに置き換える作業は、直接三重県の事務所に来てくれる代理店を紹介してもらい、実際にテンプレートを作る過程を一緒にやってもらった。オンラインではなく、隣で同じ画面を見ながらのサポート体制がキーだったとメンバーは語る。
そうして操作をマスターしたプロジェクトメンバーから、徐々に製造ラインへ展開。1日1時間程度のOJTトレーニングを約2週間行ない、ノウハウを広げていった。
同時に、製造現場で実際にi-Reporterを使用する作業者に、電子化のビジョンや目的を含め、今後の業務プロセスの改善についての説明会を開催した。なぜ紙だった品質記録を帳票ソフトに移行していくのか。その理由やメリットのみならず、その先に目指しているものまでを含め対話することを意識。また、実際に製造現場で活用するようになってからは、入力時の困りごとを日々挙げてもらい、その日のうちに改善することを心掛けた。
将来を見据えた考えをしっかり持ち、それを現場と共有すること。使う側のニーズ、改善の要望をしっかりと聞き対応すること。講習会や動画、代理店のサポートを借りながら、継続してブラッシュアップできたことが、製造ラインへの浸透を早めた。
より精度高く現場と繋がる
i-Reporter導入で作り出せた時間の活用
一番実感しているi-Reporterを導入したメリットが、ファイリングされた膨大な量の紙からの検索、紙からのExcelへの転記などにかかっていた人員や時間などの管理コストの削減だ。
月に200分を要していたファイリングは、電子化することにより0分に。1帳票あたり20分かけていた検索時間も、5分以内で確認可能になるという大きな時間短縮の成果があった。また電子管理となったことで、年間15,000枚の帳票を保管していた管理スペースも不必要となった。
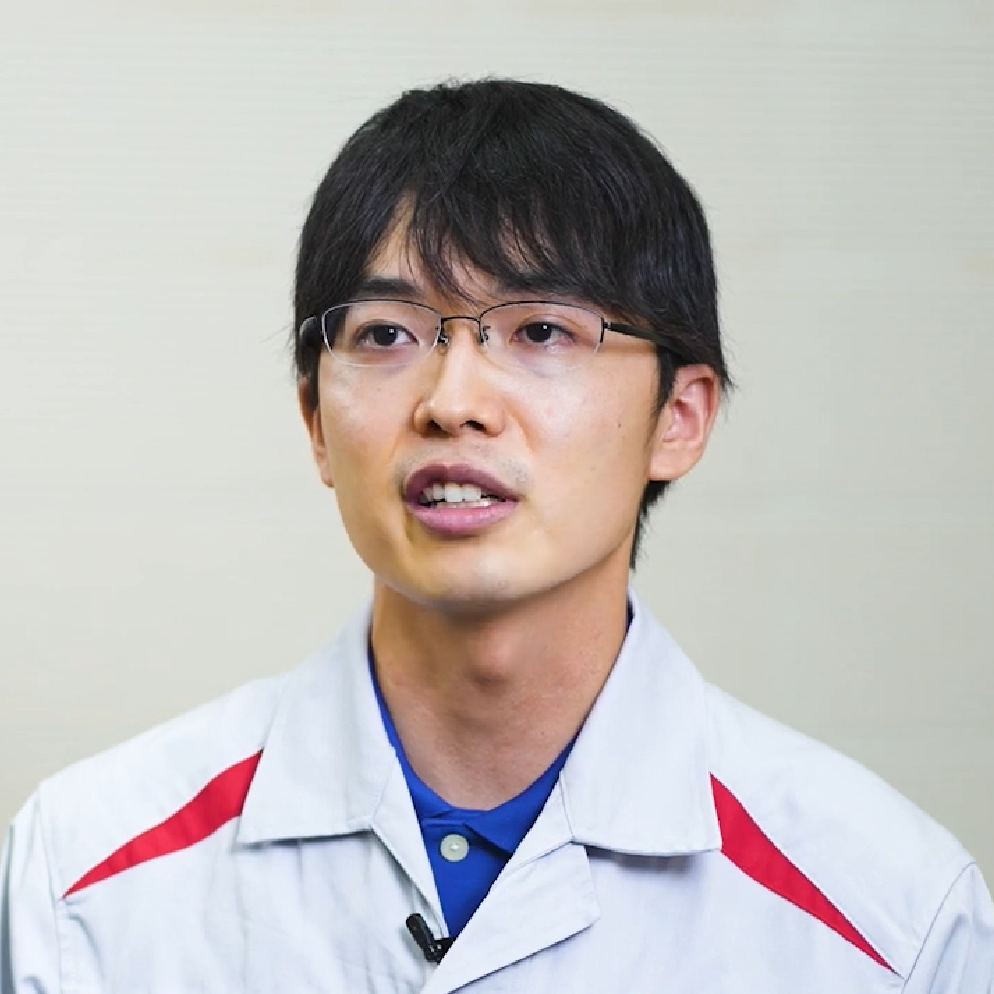
「以前は数日かかっていたデータ検索が速くなり、手間が削減できた感覚があります。改善されて、アナログな情報を集める時間が無駄だったと改めて感じていますね。i-Reporter導入で創出できた時間を分析やビジュアル化に充てることができ、さらに次のアクションに繋がっています」
蓄積されたデータの中から必要な情報を素早く取り出し、ビジュアルに変換して分析。より精度を高く「現場」を見ることができるようになるため、フィードバックや改善の質もアップする。これからも現場とともに電子化を進め、それを現場や製品の改善に繋げていく。
なお、今回の取材の模様を動画にまとめてあるので、併せて確認いただきたい。

導入企業プロフィール

古河電気工業株式会社
- 設立:
- 1884年
- 本社所在地:
- 〒100-8322 東京都千代田区大手町2丁目6番4号(常盤橋タワー)
- 事業内容:
- 光ファイバー・電線・ワイヤーハーネス等の製造 ほか






